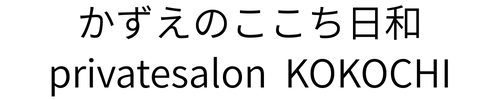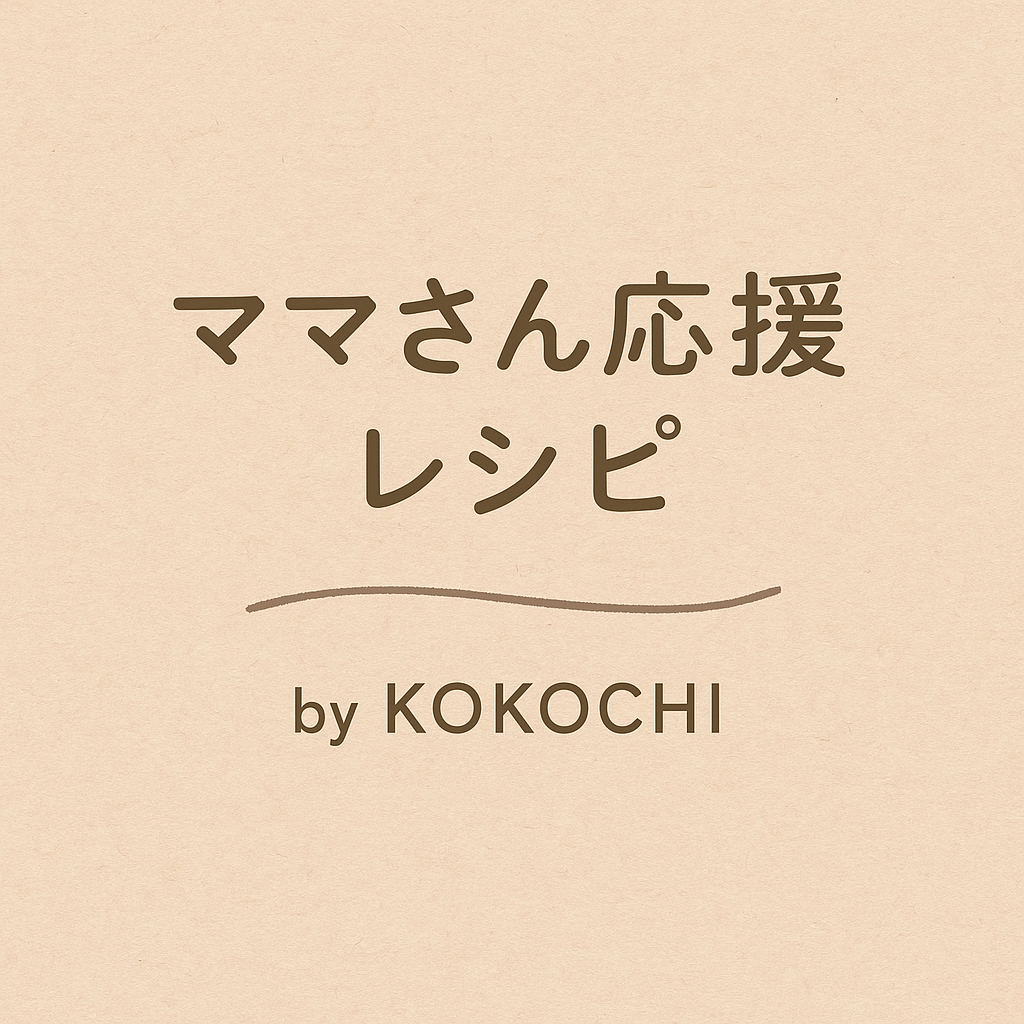KOKOCHI流・脳活コラム
先日、お客様との会話の中で「パーキンソン病」の話題になりました。年齢を重ねると「最近ちょっと動きが鈍い」「やる気が出にくい」などの小さな変化を感じることがあります。鍵を握るのは、脳の「ドーパミン」。ワクワク・やる気・達成感を生み、動きをスムーズにする大切な神経伝達物質です。
パーキンソン病とは?
脳の黒質で作られるドーパミンが減少し、運動調節の回路がうまく働かなくなる疾患です。完全に防ぐ方法は確立されていませんが、生活習慣でリスクを下げ、進行を緩やかにする可能性が示唆されています。
主な症状と“心のサイン”
- 静止時振戦(じっとしている時の手足の震え)
- 筋強剛(筋肉のこわばり)
- 動作緩慢(動きがゆっくりになる)
- 姿勢反射障害(バランスを崩しやすい)
さらに、嗅覚低下・便秘・睡眠の乱れ・不安や意欲低下など、早期からの“心のサイン”として現れることもあります。
なぜ「ワクワク」が大切?(ドーパミンの役割)
ドーパミンは「楽しい」「挑戦」「できた!」という体験で分泌が高まり、前向きな気持ちと運動の滑らかさを後押しします。つまり、楽しく動く=脳のトレーニングです。
KOKOCHI流:予防と対策(生活でリスク低減)
1. 運動を習慣に
- ウォーキング・ストレッチ・筋力トレーニングで血流と神経の健康をサポート
- 有酸素運動(歩く・サイクリング・スイミング)も◎
- ビジリスで骨盤底筋&体幹を刺激 → 姿勢・呼吸・循環が整い、脳の活性化に
- かずえのストレッチで全身をゆるめ、笑いとともにリラックス(α波タイム)
2. 食でドーパミンを“育てる”
- ドーパミンの材料チロシン:卵・大豆製品・煮干し・青魚・ナッツ
- 抗酸化たっぷり:緑黄色野菜・ベリー・柑橘・オリーブオイル
- 動物性脂肪(バター・ラードなど)の過剰摂取は控えめに
3. 生活習慣で脳を守る
- コーヒーを適量(個人差あり)…リスク低下の可能性が示唆
- ストレスを溜めない:趣味・会話・感謝・笑顔の時間を増やす
- 農薬や化学物質への曝露は最小限に
- 十分な水分摂取で脱水予防
- 睡眠の質を高め、脳の回復時間を確保
ポイント:「頑張り続ける」より「ここちよく続ける」。小さな達成感を毎日積み重ねることが、ドーパミンを満たす近道です。
まとめ:ここちよい習慣が未来を変える
パーキンソン病の完全な予防法はまだありませんが、動く・笑う・食べる・整えるという基本を丁寧に重ねることで、脳の健康は確かに育ちます。KOKOCHIは「ここちよく続く」を合言葉に、みなさんの毎日を応援します。
次回予告
次回②は「出す&増やす習慣(ビジリス+ストレッチ)」。体を動かしてドーパミンを高める、具体的なルーティンをご紹介します。